僕の父親は、僕とは正反対の性格で、楽天的で先のことを計算しないような性格でした。
僕の母親は父親について「あの人は、子どもがそのまま大きくなったような人で、私やあんたのことはなんにも考えてない、無関心な人やから」と事あるごとに、子供の僕に言っていました。
遊んでくれなかった父
父は僕と遊んでくれたことがほとんどありませんでした。
小学生だった僕は父とキャッチボールをしたいといつも思っていて、「キャッチボールしよう」と声をかけ続けたのですが、めんどくさがってしてくれてませんでした。
ただ、たまに嫌々してくれることがありました。
嬉しくてボールを父のグローブに向かって投げるのですが、5分もすると、父は疲れたと言って家に戻っていきました。
そんなふうにキャッチボールをしてくれたことが人生で3回、ありました。
父は休みの日は、お酒を飲みながら横になり、いつもテレビを見ていました。
仕事の日も、でろんでろんに酔っ払って帰ってくることが多くて、毎日浴びるようにお酒を飲んでいました。お酒がないときは、料理酒を飲んでいるときもありました。
そして他にも、父はタバコとパチンコと、阪神タイガースが好きでした。
家族で旅行に行くような家庭でもなかったし、父は僕と話をするような人でもなかったので、父との接点はほとんどありませんでしたが、阪神タイガースの野球中継は一緒に見ることが多かったです。
最初は、野球を見ていてもつまらなかったのですが、やることがなく父と一緒に野球を何度も見るうちに面白く感じるようになっていきました。
そして、阪神の選手の話や野球の話をすると、父は嬉しそうに僕と話をすることが多かったです。そのときの父はとても生き生きとしていました。
父は、自分の関心のあることになると、周りが見えないくらいそのことに集中して、生き生きしてくるような人でした。
子供以上に子供な父
ある日、僕は、近所の子どもたちと野球をしていました。
僕が当時、住んでいたのは、田舎の集合住宅のようなところでした。
田舎のある一箇所に、家が集中してかたまっているようなところで、家の前の道路で、プラスチックのバットと柔らかいボールを使って野球をしていました。
あんまり記憶が定かではないのですが、父が木製の自分のバットを持って、僕たちの野球に参加したときがありました。
父は、いいところを見せたいのか、野球に全力集中していました。
よく大人は、子供と勝負事をするときに、手加減をしてわざと子供を勝たせるということをしますが、僕の父はそんな概念が頭の中に存在しないような人でした。(いま思い返すと、そういうところは好きだなと思えます)
なのでこのときも相手が子供だとか関係なしに、というか「父が一番子供のよう」に、やる気満々でいました。
そして、ピッチャーである近所の子供の投げたボールを、バッターボックスの父は猛烈にフルスイングしました。
すると、ボールではなく、父の持っていた木製バットがものすごい勢いで、父の手から離れ、グワングワンと回転しながら、近所の子どもの家の二階の窓ガラスを直撃しました。
「バリン!」という音とともに勢いよく窓ガラスが割れ、バットはその家の中に吸い込まれていきました。
僕も、近所の子供も、それを見て呆然としていました。
そのあと父は「しまった!」といい、自分の家に帰りました。(リビングで横になりながら野球中継を見てくつろいでいたようでした)
取り残された僕たちは、すごく微妙な空気になり、僕は恥ずかしくて、彼らに謝りました。
とりあえず、みんな家に帰ろうという話になり、家に帰りました。
しばらくして母親が仕事から帰ってきました。
僕は、何が起こったのかを母に伝えました。
父は謝りに行くこともなく、家でずっと野球をみていたことも付け加えました。
母は血相を抱えて父を怒鳴り、僕と母で、その近所の家まで謝りにいきました。
家の人はカンカンに怒っていて、母はとにかく謝り続けました。
そして、家に戻った母は、もう一度父に怒鳴りつけました。「なんで謝りにいかんのよ!?」「バットが家の中の人に直撃してたら、どうするつもりやったん!?」と、激怒していました。(そりゃそうだ)
父はあっけらかんとしていて、「もう、終わったことやし、ええやろ」というような言葉を返し、母の火に油を注ぎました。
父は、とくに気にしていないようでした。
僕が5歳のときにも、事件は起こりました。
家族三人で、晩ご飯の「日清カップヌードル」を食べていたときのことでした。
僕は自分のカップラーメンを間違えて、ひっくり返していまいました。そして熱々の汁が全部、自分の腕にかかり、僕は大泣きしました。
慌てた母が、僕を病院に連れて行こうと支度をしているときに、父は食卓から動かずにカップヌードルを食べていました。
母が「あんた、こんなときに、なんしよん!」と父に怒鳴ると、父は「ちょっと待て、麺が伸びるやろ。全部食べてからにしよや」と言いました。
目の前で大やけどを負ってギャン泣きしている僕よりも、100円のカップヌードルを優先する父に、母はまた激怒しました。結局、母と僕の二人で病院に向かいました。
このときの光景は、いまでもうっすらと覚えています。
そして病院で処置をしてもらいました。このときのやけどの痕は、35歳になった今でも残っています。
これが僕の父でした。
父の武勇伝
人の話には興味がない父だけど、自分の話をするときはいつも生き生きしていました。
ちなみに父の最終学歴は中卒で、そのあとは重機の修理をする仕事をしていました。
父がよく言っていたのは「小学生時代の父は、理科が天才的だった」ということでした。
いつも理科のテストで100点を取っていたことを、僕によく自慢していました。
小学校の理科のテストが100点というのは、すごいのかどうかよくわからないけど、とにかく父の中ではそれが誇りになっていたようでした。
他にも、父は中学生時代には柔道部で、一番背が低く体が小さいのに「副将」をしていて、自分より大きな相手を投げ飛ばすということで、他の学校の柔道部を驚かせていたという話もよく聞きました。
中学を卒業したあとは、愛媛を出て、大阪に引っ越したようでした。
そしてある日、大阪の路上でヤクザに絡まれたそうです。
腹が立った父は、反射的にヤクザを背負投げしてしまいました。そして「あ、しまった。殺される」と思った父は、その場から猛ダッシュで逃げて、ヤクザに殺されないように、また愛媛に帰ってきたようでした。
UFOを見た父
父が大阪に住んでいた頃、父は路上にいるホームレスの人に声をかけて、一緒に屋台でお酒を飲むのが好きでした。
毎日、いろんな人に声をかけて、飲み明かし、友達をつくっていたようでした。
そんなある夜、屋台でホームレスのおじちゃんと一緒にお酒を飲んでいると、夜空にUFOが浮かんでいるのが見えたそうです。
その飛行体は、不規則な動きで動いていたので、飛行機ではないということでした。
そして、そのUFOを見ていると、中にいる宇宙人が父になにかメッセージを送っているのを直感で感じたそうです。
そのときに、隣りにいたおじちゃんにUFOが見えたかどうか聞くと、「見えない」といわれたそうです。父は「バカいえ、あそこにあるやろ」と指をさしたけれども、「なにいってんねん」と返ってきたそうです。
おじちゃんには見えなかったそうです。
そして、父は僕に「確かに見た。UFOは実在する」と興奮気味に話しました。
父との最後の会話
それから10年が経ちました。
僕は大人になり、精神疾患にかかるも、リハビリを少しづつすることで回復し、週三勤務で仕事に就いているというような状況でした。
一人暮らしをしてからは、父と話すことはなくなりました。
そのとき父は、すでに僕の母と離婚をしていて、独り身の状態でした。
父から連絡が来ることもないし、父に連絡をすることもありませんでした。
ただ、どきどき父から「お金を貸してほしい」と連絡が来ることがありました。
父にお金を渡す約束をして、集合場所で父に会い、軽く話をしたときに父は「いまの仕事をやめるんよ。自分がやりたいことをやろうと思ってな」と僕に言いました。
そして僕は「いいね、人生楽しんでね」と返しました。
当時、父には多額の借金がありました。
なので、毎月の給料をもらいながら返済をしていたようでしたが、仕事をやめてどうやって借金を返すのかと、少し心配になりました。
だけど、それを考えると、僕もしんどくなるので、僕は考えるのをやめました。
そして2分ほどの短い会話のあと、父はオンボロの自分の車に戻り、去っていきました。
警察から突然の知らせ
ある日、警察から電話がかかってきました。
電話に出ると、神妙なトーンの男の警察官が僕に、父が自宅で亡くなっていることを告げました。
その警察官は「いまからこちらに来れませんか」と僕に尋ねました。
僕は「風邪をひいているので、行きたくありません」と答えました。風邪をひいていていたのは事実だけど、それとは別に、どうでもいいような、めんどくさいような気持ちがありました。まともに僕を相手にしてくれなかった父に対して、恨みのような感情をもっていたからです。
それでも、いかないわけにはいかなかったので、父の住んでいた市営住宅へ向かいました。
部屋には、裸の父が仰向けで転がっていました。
すでに医師による検死が行われていて、原因はわからないが、なにかの病気だろうということでした。
僕は心のなかで「そりゃ、そうだろう。あれだけ酒とタバコを吸ってりゃ、そうなるだろう」と醒めた気持ちでした。
悲しい気持ちにはなりませんでした。
父の死体を眼の前にして、僕は父に対する恨みのような気持ちがどんどん湧いてきました。
年配男性の警察官が、僕に同情を示しながら「つらいでしょう」と声をかけてくれました。僕は「ひどい人だったので、なんとも思いません」と返しました。すると「そんな言い方は…」とショックを受けたような反応が返ってきました。
もう一人の若い男性警察官は、君の気持ちはわかるよと言いたげな笑みをうっすらと浮かべながら、同情は示さず、淡々と仕事をこなしていきました。
このとき僕は、年配の警察官に心を癒やされ、若い警察官に怒りを感じていました。
本当は父親に愛されていたんじゃないか
僕のパートナーの仕事が休みの日に、一緒に父親の部屋の片付けをしに行くのが僕たちの日課になりました。
父の散らかった部屋を見たパートナーは、その部屋に充満していたであろう悲壮感を感じとったように見えました。
僕はパートナーに「悲しくもなんともない」ということを伝え、父親のこれまでの態度を説明しました。
すると、パートナーは「昔は、君がいうように、お父さんは君のことを気にしていなかったのかもしれない。でも、君のお母さんと離婚して、この市営住宅に引っ越して、一人ぼっちになって、そこではじめて気付いたんじゃないかな。大切なものを失ったことに」と言いました。
僕は「まさか」と笑って、相手にしませんでした。
父の台所のシンクには生ゴミや水が溜まっていました。掃除をしようとゴム手袋をはめて、水を抜き、排水口のカップを引き抜くと、10匹くらいのゴキブリがいっせいに沸き立ちました。
僕は気持ち悪くて、シンクに近づくことができなかったので、パートナーが代わりにシンクの掃除をしてくれました。
ある日、僕のもとに一通の手紙が届きました。
父が市営住宅に住んでいたときに、父の家によく通っていた女性からの手紙でした。その女性は、母が精神病棟に入院していたときに知り合った人で、母と父の共通の友人でした。
そして、父の死体を最初に発見してくれたのが彼女でした。
その手紙には、まず最初に父との生活が書かれていました。
彼女は、いいパートナーを見つけるために、料理を習いたかった。そこで、父がカレーの作り方をよく教えてくれた。そして、彼女がつくったカレーを美味しいと褒めてくれた。話や悩みもきいてくれた。いい友達だった。男女の関係はなかった。
そんな話から始まりました。
そして「私はりゅうやくんに謝らないといけないことがあります。それは、部屋にあったりゅうやくんの私物をリサイクルショップで売り払ってしまったことです(彼女はお金がなかった)。このことは、謝っても謝りきれません。私は最低のことをしました。許してもらおうとは思っていません、ただ本当にごめんなさい。」と続きました。
「その中で、りゅうやくんが幼かったときによく着ていたハンテン(服)を売ろうとしたときに、りゅうやくんのお父さんから、それだけは売らないでくれと言われました」
と手紙にはありました。
そして、リサイクルショップで買い取ってもらった金額が、現金として手紙に挟まってありました。
僕は、彼女が僕のものを勝手に売ってしまったことについては全く怒っていなかったので、母親を通じて彼女にそのことを伝えました。
そして、そのときに母親と電話で話してわかったのですが、父はどうやら仕事をクビにされたようで、母にはそのことを伝えていたようでした。
父が30年間勤めていた会社は、父と父の友人の二人で立ち上げた会社らしく、父の友人は社長としてそのまま残っていたけど、父は次第に会社を追い出されるようになったということでした。
父は僕に「仕事を辞めて、人生でやりたいことをやる」と伝えていましたが、本当はクビになり、会社を追い出されたようでした。
ある日、僕はひょんなことから、当時住んでいたアパートの大家さんと居酒屋で一緒に飲むことになりました。
そこで、僕は父親の話をしました。
父親の気持ちが最後までわからなかった、と。
すると、大家さんは「◯◯くん、本当のところはわからんのやけど、話を聞く限り、君のお父さんは相当不器用な人やったんやないかなぁ」と言いました。
そうなのか、と思いました。不器用だったのだろうか、と。
そして一人で家にいるときに、父の部屋を片付けにいったときのパートナーの言葉と、父の友人の手紙にあった言葉と、クビにされたことを隠していた父のことと、大家さんの言葉が蘇りました。
「昔は、君の言うようなお父さんだったのかもしれないけど、一人になって、自分が失ったものの大きさに気が付いたんじゃないかな」
「そのハンテンだけは売らないでくれ」
「父は、借金漬けの中クビにされたけど、人生でやりたいことをやりたいと僕に嘘を付いた」
「君のお父さんは、相当不器用な人やったんやないかなぁ」
父は、本当は僕のことを愛してくれていたんじゃないか。
じゃあ、なぜそれを見せてくれなかったんだ。僕のことを全く相手にしてくれなかったし、心配もしてくれなかった。僕の話なんて、一度だって聞いてくれたことはなかった。自分の話だけだった。愛情を示すチャンスはいくらでもあったじゃないか!
でも、大家さんがいうように、かなり不器用な人だったのかもしれない。
借金漬けのなか、仕事をクビにされ、素直に人に気持ちを伝えられず、助けを求められず、病気で身体が弱っていくなか、お酒を飲み酔うことで、どれだけその状況に耐えられていたんだろう。どんな気持ちだったんだろう。そのときに僕のことを考えたのだろうか。
もう話すことはできない。
そう思うと、一気に涙が出ました。











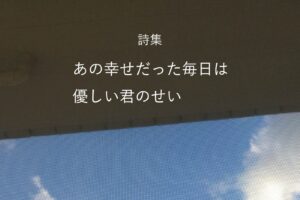
コメントが欲しくてたまりません、どうかコメントを…!!