これは、過去のトラウマの記録です。
この記事は、見ていてしんどくなるような内容が含まれています。調子の悪い方や、暗い話を聞きたくない方は、ここで引き返してください。
僕が高校生の時の、印象的だったエピソードの内の一つを書きます。
まず基本的な情報として、母は身体的虐待と経済的虐待を受けて育ちました。そして、躁うつ病になり、「苦しい」「死にたい」「殺してくれ」と毎日泣いたり、叫んだりしていました。
父は酒とタバコとパチンコが好きで、僕や母には全く関心がない人でした(「お父さんは子供がそのまま大きくなったような人」「私やあんたのことなんて、なんとも思ってない」と母親にたびたび言われて育ちました)。
父は精神疾患に対しての理解が全くなく「なんで、お前はいつもそうなんぞ!」とか「いい加減、甘えるのをやめろや!」とか、そういう心無い言葉をいつも母にかけていました。
僕はそんな父に理解を促すために、精神疾患のことを説明したり、うつ病についての本を買って父に渡しましたが、父は全く聞く耳を持たず、本も1ページも開かれていませんでした。
なので僕の高校生時代は、母に対しては「大丈夫よ。お母さんが悪いんじゃなくて、病気が悪いんだからね」と、愚痴や泣き言や怒りや叫びを聞いて世話をし慰めて、父に対しては「なぜ母の苦しい気持ちを考えようとすらしないんだ」と言い合いや喧嘩をする毎日でした。
母には「寂しいから、そばにいて」「一人にしないで」といつも言われ、僕はいつも母のそばにいました。
なので、クラスメイトから遊びの誘いが来ても、すべて断っていました。
ですが、ある日「今日は寂しくないから、遊びに行っても大丈夫よ」と母に言われ、クラスメイトの家に行きました。そして、ちょうどその家のチャイムをならす直前、僕の携帯電話が鳴りました。
「寂しいから帰ってきて」と母に泣きながら言われました。クラスメイトとの遊びを断り、すぐに家に帰りました。
本題のエピソードに入りますが、それは土曜日で僕の学校が休みの日でした。僕の家は二階建てで二階にみんなの寝室がありました。
朝、起きた時(昼前頃ですが)、隣の部屋に母がいませんでした。僕はいつも遅くまで寝ていたのでこういうことはよくあるのですが、その日は家に漂う空気がいつもと違うことにすぐに気が付きました。なにか嫌な予感がして、すぐ一階に降りました。
すると、母がソファーで横たわっていて、ソファーの前のテーブルの上にコップがあることに気が付きました。それを見てすぐに、自殺を試みたんだとわかりました。黄色いコップの中には溶けた薬の錠剤が白い塊になってコップの底に少しへばりついていました。
すぐにお母さんに声をかけました。
母はうつろな声で「救急車は呼ばないで欲しい。このまま死なせてほしい。やっと楽になれる」と僕に頼みました。「りゅうやのピアノを聞きながら死にたい」と言われました。
僕は救急車を呼びませんでした。
母が死んでしまうのは自分が壊れそうな位つらいことだけど、母の苦しむ姿をずっと近くで見ていた僕には、母の言葉が理解できたからです。
母の頼み通り、横になっている母の隣でピアノを弾き続けました。当時、鬼束ちひろの「月光」という曲が大好きだったので、この曲ばかり練習していて、この曲だけ弾けるようになったので、この曲を何度も繰り返し弾きました。
弾きながら涙が止まりませんでした。
ずっと涙が出続けていました。
弾きながら、母の、呼吸から次の呼吸までの感覚がどんどん長くなっているのがわかりました。
その日は晴れていて、穏やかで柔らかい日差しがリビングに差し込んでいたのを覚えています。
母がどんどん死に近づいていっていることを母の呼吸から感じ取り「お母さん、本当に死ぬんだ」「大好きなお母さんが、本当に死ぬんだ」「もう二度と会えないんだ」と悲しくてたまりませんでした。
僕が中学生になったころから母の体調が悪くなりました。それ以降、母の笑顔を見ることが出来なくなっていたので、僕の母はいつも暗い表情というイメージでした。それより前の、僕が小学生や幼稚園児だったころの母の記憶はほとんどありませんでした。
ですが、小学生低学年か幼稚園児だったころの記憶が二つ残っています。
一つ目は、僕はよく「お母さんが死んでしまう」という想像をして悲しくなって泣いていました。そしてお母さんになんで泣いているのと聞かれ理由を話すと笑っていたような気がします。その想像は、いつも夕暮れの踏切でカンカンカンと踏切がなっていて、僕はその踏切から少し遠くにいて、お母さんが「じゃあね、りゅうや」と言い、電車にひかれて死んでしまうというものでした。
二つ目は、母と近所の公園に遊びに行った時でした。僕は砂場で、砂遊びに夢中になっていたのですが、ふと気が付くとお母さんが居なくなっていました。僕は物凄く悲しくなりその場で泣きました。しばらくして茂みでわざと隠れていたお母さんが笑顔で現れ、「ごめんね、どうなるかと思ってわざと隠れてみたんよ。」というようなことを笑顔で言っていたような気がします。そんなことが出来る元気なお母さん、笑顔のお母さんは、その記憶が最後でした。
死んでゆく母の横で泣きながらピアノを弾いているとき、そんなお母さんの思い出や優しさが蘇り、それで、ますます悲しくなり泣き続けました。ですが、耐えました。
そのときは、とにかく悲しくて涙が止まらなかったこと以外の感情は覚えていません。
そして、その日はたまたま父が仕事から早く帰ってきました。
家の様子を見た父は「なんしよんぞ!はよ救急車呼べや!」と電話を取りに行きました。僕は父に向って「お母さんを楽にさせてあげろや!」「誰がここまでお母さんを苦しめたんか、分かっとんか!」と電話が出来ないように、受話器を押さえつけました。
ですが、父が力づくで電話をとり救急車を呼びました。
僕は受話器を押さえつけていましたが、力負けをしたふりをしていました。本当は、お母さんに死んでほしくなかったからです。







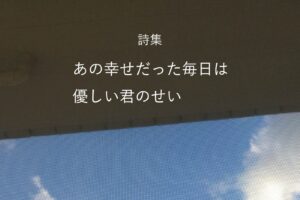



コメントが欲しくてたまりません、どうかコメントを…!!